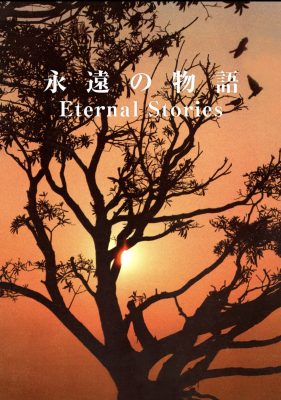自分が巳年だからか蛇に割と愛着がある。動物園でも爬虫類館が好きだった。蛇は、ヒンドゥー教ではナーガという蛇の神様もいらっしゃるし、日本でも白蛇は縁起が良いとされているように、どこか神秘的なところがある。特に目が神秘的だ。
ところがそんな私にとって、昨年は蛇の生殺しのような期間(!)から始まった年だった。

毎年、寒い一月頃、いつも艶やかに姿を見せる。
昨年の元旦、眼に不調があり救急病院へ行き、大学病院で精密検査するまで安静に、と指示を受けた。目の不自由な方に付き添う仕事をし、目の知識だけは頭でっかちだったため、最悪の眼の事態を想像した。じっと待つしかない長い休み期間は、まさに蛇の生殺し状態だった。
休みが明け、大学病院で精密検査したが原因不明。ところが気持ちが切羽詰まっていたからか、その時の医師の、何げない一言に傷付いた。次週、別の検査となったが、不信感を抱いたまま同じ医師に診てもらっても納得できそうになく、それにまたこのまま一週間待つ…、と思うと途方に暮れ、家族に相談した。家族は、昔に家族がお世話になった個人眼科を受診するのも一案、と提案してくれた。セカンドオピニオンだと考え、家族が信頼する先生の診断なら納得できるはず、とその眼科へ行った。私の目的は、別の先生による真っさらな診立てを知ることだったから、最初に救急病院へ行ったこと以外の、大学病院のことや家族から紹介を受けたことは特に話さないことにした。ただ純粋に眼の症状だけを診てほしい、真実が知りたいと、その時は思っていた。
その眼科は、地元の人に愛されているような、こじんまりとした和やかな雰囲気で、患者さんとスタッフの方たちの朗らかな会話が、ゆったりと流れていた。そこでボーっと順番を待っていると、自分の眼のことだけでいっぱいの張り詰めている自分に気付いた。名前を呼ばれ、小学校の保健室にあったような、視力検査の黒いスプーンみたいな懐かしい器具を手渡され、片眼ずつを覆い、看護師さんが手作業で視力検査から進めていかれる。幾つかの検査が終わり、いよいよ部屋の一角にある小部屋に入る。まるで洞窟のような真っ暗な空間。闇を照らす煌々としたライトを額に付けた、ちょっと怖そうな男の先生がおられた。先生は、理科室にあったような眼の模型やイラストなどを使い、熱心に丁寧に症状を説明された。どうなるのか、はっきりと原因が知りたかった。爆弾を抱えたまま安静に過ごすなんて嫌だった。だけど先生は、私の質問に対して、科学ではどうしても原因の分からないこともある、今は様子を見るしかなく、申し訳ない、と説明された。その謙虚な説明のされ方に驚きながら、なぜ原因不明かということにも納得し、治療方針をお伺いし、お礼を伝え診察室を出ようとした。
すると「〇〇さんのご家族ですね」とおっしゃった。「(保険証の)住所を見れば遠い所からわざわざここへ来られるのもおかしいし、分かりましたよ、〇〇さんお元気にされていますか?」と。先生は、家族の眼のことを大切に思われ、一人の医師として、かつて診た患者の将来を案じておられたことが分かった。そしてなんと突然、涙を流された。びっくりした私は家族がここを勧めてくれたこと家族の眼のこと、元気にしていることを伝えた。忙しそうな診療時間中にもかかわらず、先生は真っすぐに私の目を見ながら真剣な表情でずっと話を聞かれた。先生の真心のような、尊いものが伝わってきて胸が熱くなった。

咲き始めた!
次の診察は一週間後。私は大学病院の経緯を話してないことに引っかかりだし、これで本当にいいのかな、と思った。自分が決めた方針だったし、だからこそ診断にも納得できた。嘘を付いた訳でもないし何も悪いことはしてない。でも、と思った。繰り返し考えた。今思えば、些細なことをわざわざ取り上げ大層な問題にしていたのかもしれないが、その時は無視できなかった。私はトゥリヤーナンダ(インドの聖者の方)が好きで、かつてヨーガの仲間の前でそのことを話したことがあった。トゥリヤーナンダがある弟子に言われた言葉があり、よく心の中で唱える。
「悟りは強く、純粋で、真っ正直な者だけに与えられる」
明日は診察日という日の夜、お風呂の湯船の中でもその言葉を唱えていた。ふとその時、トゥリヤーナンダからの言葉が聞こえてきた。(気がした!)
「なぜできないのか。もし君が彼を本当に愛しているのなら、彼が知らないことを知らせてあげることをなぜ躊躇するのだ。愛している者に向かっては、何でも話すことができるはずだ。人を愛する時、どうしてそこに恐れなどがあり得よう」
瞬きもせず、じっと話を聞かれた先生の眼差しが焼き付いていた。その先生に、話せないことがあるのはおかしい、やっぱりありのままを話そう、と思った。先生が仕事をされる上で必要な情報かもしれない。患者の役割があるとすれば、それを果たさなければいけない。
「彼(先生)が知らないことを知らせるのになぜ躊躇するのか?」。 今更知らせれば私が医者に不信感を持っている人という悪い印象になる、そうなると家族にも迷惑が及ぶ、それに大学病院の診立てを伝えれば先生の診方も変わるかも…、次から次へと奥に潜んでいた自分への保身、人への疑い、恐れが浮かび上がる。でも「人を愛する時、どうしてそこに恐れなどがあり得よう!」。トゥリヤーナンダのこの言葉は、あまりにも力強すぎて、私のしょうもない拘りの思いを吹き飛ばした。もう自分の眼がどうなるかとか、眼に対しての本当のことが知りたいとか、もうそんなことはいいやんかと思えた。先生の真っ直ぐな眼差しはトゥリヤーナンダの眼差しと重なった。私も真っ正直でありたい!と、不安が全くなくなった。
翌日の診察日、先生に、ありのまま経緯を伝え最初から話さなかったことを謝った。すると「そうです、真実を話してほしいのです」 先生の声が、洞窟のような暗室に響いた。ドキッとした。真実を、真理を軸にしてきたつもりだったから。先生は続けて、小さな町医者ではどうしようもないことがあります、もうここでは診られないという時にはすぐに信頼する大学病院の医師を紹介します、とおっしゃった。私にできる限りのことをここでします、と真摯に話された。胸が詰まりそうだった。
それからしばらく通院し、眼は治っていった。先生は、どうして治ったのか分かりません、薬の効果か分からない、あなたの自然治癒力で治ったのかもしれません、よかったです、ととても喜ばれた。そんなことを正直に言われる病院の先生に会ったことがなかった。最後の日に先生は、私は医師としては失格です、と言われた。涙を流したことを恥ずかしそうに謝られた。医師は、力士が土俵上では決して感情を出さないように、どんな時も淡々と行為しなければいけないのです、と自分を戒めるようにポツリと話された。私は先生のことは全然知らないが、先生には先生の精進されている道があり、先生も私もみんな同じなんだと思った。私は私の信じるヨーガの道を誠実に歩みなさい、と教えられたようだった。そして、真っ正直とは理屈じゃない、それが真理だった。真理に対して潔白でいること、誠実でいること。自分が切羽詰まろうが、張り詰めようが、そういう時こそ、だった。トゥリヤーナンダが真っ正直な先生の姿を通して、教えてくださった。そして、そこは師のお膝元でもある北野天満宮のお側だったのも単なる偶然とは思えなかった。(思い込みだろうか⁈)

最近、近所の山で偶然見つけた、木・石・牛だけの小さな拝所。
真理に対して間違ったことをしている時には自分で気付けますか? と師にお尋ねしたことがある。師は「自分で気付くし、結果が教えをくれることもあるし、また第三者が教えをくれることもある」とおっしゃった。
師の恩寵の下、周りの人や環境からどれほど与えられているか。私は真理を軸にできている! なんて奢らないように、古い自分からは蛇みたいに脱皮を繰り返していきたい。そういえば、蛇は脱皮する前の期間じっと動けなくなるという。ということは、もしかして私のあの時も、生殺しではなく脱皮前の…⁉ (また都合よく解釈 笑。もはや願望) とにかく!常により良く変身していけるように、何度でも脱皮するため(笑)やっぱりいつも唱える。
「悟りは強く、純粋で、真っ正直な者だけに与えられる!!!」

冬に際立つ。木の枝の美しさ!
野口美香


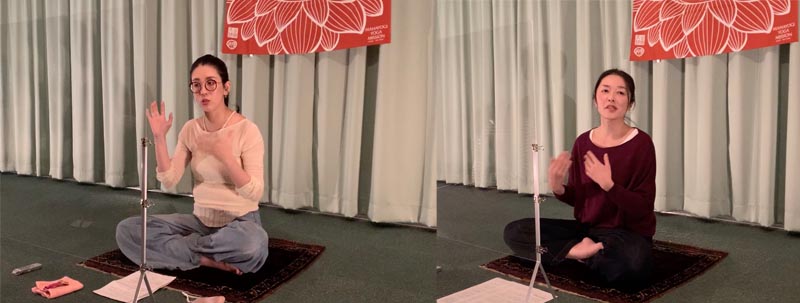





 ゴーパーラ
ゴーパーラ