ヨーガ・瞑想クラスに参加されている方へのインタビュー第二弾!(前回の記事はこちら)
 5年ほど前には、インドの北から南まで旅をしてアーシュラマ(道場)に滞在したこともあるという藤井かおりさんにお話を伺ってみました。クラスに来られて3年が過ぎましたが、彼女を見ていると姿勢が美しく変わり、体の軸がしっかりしてこられたのがよ〜く!わかります。
5年ほど前には、インドの北から南まで旅をしてアーシュラマ(道場)に滞在したこともあるという藤井かおりさんにお話を伺ってみました。クラスに来られて3年が過ぎましたが、彼女を見ていると姿勢が美しく変わり、体の軸がしっかりしてこられたのがよ〜く!わかります。
——ヨーガと出会いどのような変化を感じていますか?
以前は呼吸が浅く、息苦しくなることもありましたが、今は日常で気持ちのよい呼吸ができているように感じます。
また、物事を自分のいいように解釈したり、都合の悪いことは見ないようにしていた部分があったのですが、ありのままを受け止めて、前向きに捉えられるようになってきました。
——藤井さんにとってクラスはどんな場所ですか?
心が落ち着く場所です。クラスの後、何日かはその余波が続きます。
みんなでアーサナをするとすごく集中できるし、穏やかな気持ちになるので、やっぱり行くとぜんぜん違うなあと感じます。
——ヨーガを続けている理由は何でしょうか?
ヨーガは、私にとって一生学んでいられると感じる大切なものです。その時々で自分に必要な新しい気づきのようなものがあるからです。
例えば、日常のふとした時にヨーガの教えや、ブログに書かれていたことが腑に落ちたり、悩んでいることの解決法が見えてきたり、本当に大事なものはこっちだと、教えてもらっているように感じます。
——ヨーガを通してどのようになりたいですか?
女神を母として信仰し、信じて生きていくという境地に憧れます。神様のこと、その中にある純粋な愛をもっと知りたいです。
以前、人のためにと思ってしたことで、自分のことしか考えていないと言われたことがあり、それに対して相手を責めるような強い感情を持ったことがありました。
その時に、知らず識らずのうちに見返りを求めていた自分に気づき、考えされられました。ヨーガを通して教えを学び、本当の意味で強く温かい、愛のある人でいられたら…と思います。
軸がしっかりしてきたと感じたのは、確かなものを藤井さんが感じていて、自分の中に理想とするあり方をきちんと据えているからなのですね。納得です〜。
今回お二人からお話を伺ってみて、あぁ、こんなふうに感じてくれていたんだ〜!と初めてお聞きする内容に驚いたり、また頼もしくも感じたり、とっても楽しいインタビューとなりました。
呼吸が変わり、心が調い、そこにヨーガの教えがすーーっと入っていく。生きるということとヨーガが結びついてきて、今の実践の先に「こうなりたい自分」というものが持てるようになるんだなあと、やっぱり続けてきた中で培われていったものは大きいと感じました。私自身もとっても貴重な贈り物をいただいたような気持ちになりました。
これからも一緒に学び、励んでいけますように!
マードゥリー

クラス後に。サティヤー、二宮さん、藤井さん、マードゥリー(左から)














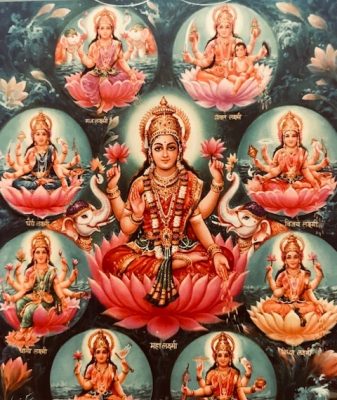
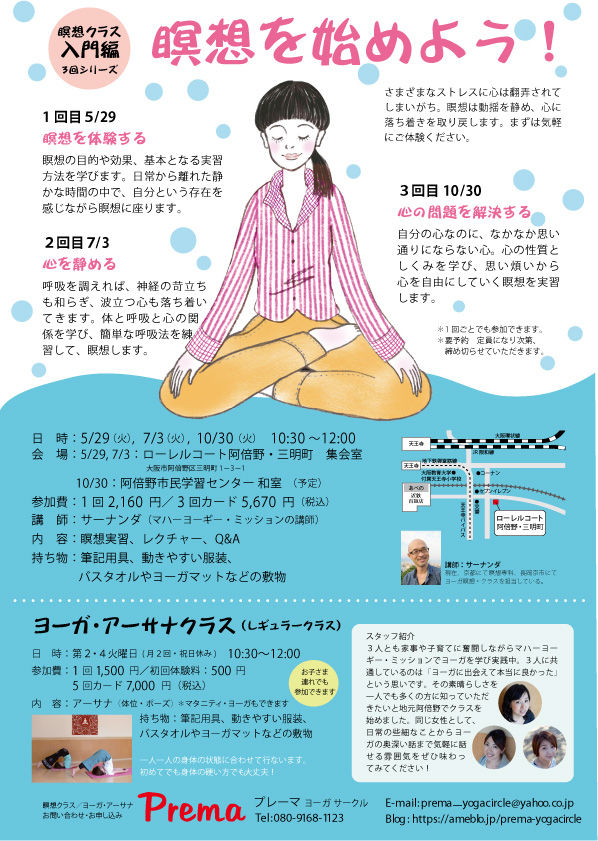

 カーリー・ヤントラでの瞑想は、最初は目を開いてヤントラの形を思い描けるようになるまで凝視し、目を閉じて姿形を思い浮かべて集中する方法だったが、ヤントラを用いての初めての瞑想だったためかヤントラの形ばかりが気になってしまい、最初は集中ができなかった。それでも続けていると、ヤントラが浮かんできてその向こうに師のヨギさんを感じることができた。さらにもっとそのヨギさんに集中していきたいと思った時に、残念ながら終了の時間がきてしまった。
カーリー・ヤントラでの瞑想は、最初は目を開いてヤントラの形を思い描けるようになるまで凝視し、目を閉じて姿形を思い浮かべて集中する方法だったが、ヤントラを用いての初めての瞑想だったためかヤントラの形ばかりが気になってしまい、最初は集中ができなかった。それでも続けていると、ヤントラが浮かんできてその向こうに師のヨギさんを感じることができた。さらにもっとそのヨギさんに集中していきたいと思った時に、残念ながら終了の時間がきてしまった。








