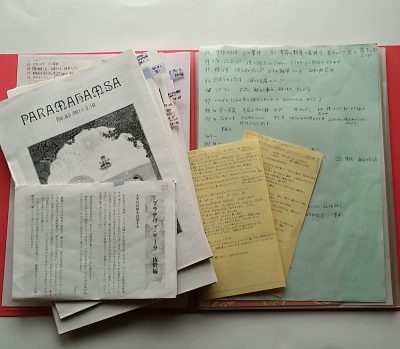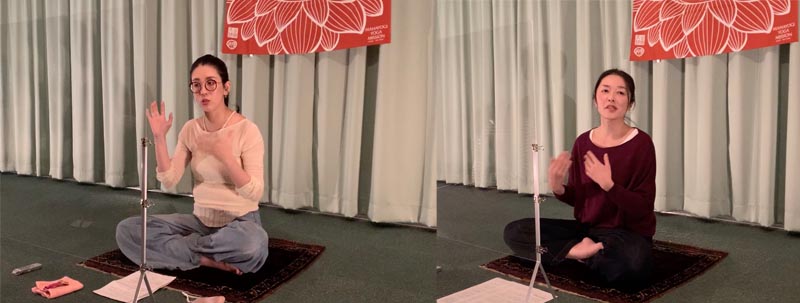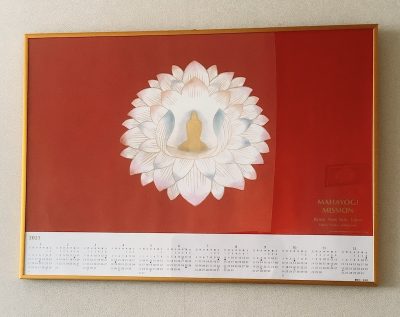新型コロナウイルス感染症は私たちの日常を大きく変えました。
私が暮らしている地域でも、医療従事者のお子さんの保育園登園拒否や、病院内駐車場の通勤車への心ない張り紙など、差別や偏見による行為を聞くことが度々あります。
過剰な不安感や間違った情報によるものがほとんどだと思われますが、決してあってはならないものです。そして、医療従事者に対してだけではなく、身近なところでも起きています。
以前にブログで少し紹介させていただきましたが、職場の鍼灸治療院に来院される患者さんにも、状況が長期化するに連れて気持ちに余裕がなくなっているように見受けられる方が少なくありません。
高齢で一人暮らしの方は、買い物に出かけることすらも怖くなり、塞ぎがちになっています。そんな気持ちを抱えて買い物に出かけた時に、家族連れが賑やかに買い物しているのを見ると、自分ばかりが我慢を強いられているようで腹立たしくなると言っていました。同じく高齢の方で日頃から警戒心が強かった方は、陽性者が出たと噂で聞いた建物には絶対に近付かないようにしている、怖くて人が歩いているのを見ると、陽性者ではないかと疑って見るようにしている、と言っているのも聞きました。 また会社勤めの方は、社内で陽性者が出た際に、その感染経路が飲み会だったと聞いて、憤りを感じて投げやりな気持ちになってしまったと言っていました。
話を聞いているとそう思ってしまう気持ちが分かるような気がして、つい感染対策に気を付けていない人達のことを一緒になって話してしまいました。でも、それを言ったところで現実は何も変わらないし、むしろ心の中がもやもやとして余計に波立つような感覚になりました。自分は感染対策に気を付けて生活しているという自負の元、会ったこともない人達に対して偏見を抱き、差別的な 発言をしてしまっていることに気付き、反省しました。
こういう何気ない会話をする中でも、互いの思いや言葉の持つ力に影響を受けているのだと痛感します。
ヨーガの教えの中に、アヒンサーがあります。非暴力の教えです。
アヒンサーは、他者(全生命)に対していかなる苦痛も与えない、という意味。それは行為はもちろんのこと、言葉で与える苦痛や心の中で思うことも含まれています。
日常生活でアヒンサーを実践していく時は、苦痛を与える言動をしないように気をつけますが、自分にはそんなつもりはなくても、言葉遣い一つで相手を傷付けてしまうこともあります。頭で分かってはいてもそう簡単にできることではありません。だから、やはり根本である思いを正しいものにしていくことが重要だと思います。

自宅近くの公園で見つけたフキノトウ。「真理は一つ」という花言葉があります。
それで、先ほど書いた通り、コロナ禍にまつわる様々な患者さんとの会話の中で、私自身がアヒンサーを実践できていないなあと感じ、改めて意識して今できる具体的なことは何かを考えました。先入観を持たない、ネガティブな話題が出ても同調しない、そういう話題に終始しないように話の方向を変える、等々。でも、何かもっと大切なことが抜けているのではと思い至りました。
それは、上辺の行為だけ調えるのではなく、「すべての生命は等しく尊い」という真理が思いの根本になければならないんだということ。
思いが正しくなれば自ずと謙虚になり、優しさに満ちた言動に繋がっていく。
ふと、昨年末のブログに書いた「愛は優しさでしか表せない」ということと、アヒンサーを実践することとは同じであるという気がして、今一度ただ他者を愛しむようにしようと決意を新たにしました。このことが根本にあれば、小さな行為でも大きな意味を持つかもしれない。最初からうまくいかなくても、謙虚さを持って訓練していこうと思い、具体的な実践を始めていきました。
- 患者さんと会話をしながらも、その人の中にある純粋な存在をイメージして感じるようにする。
- 話に安易に同調しないように気をつける。
- 揺らぎそうになったら、みんな尊い存在なのだから、と心の中で繰り返す。
- 相手の思いや言葉を否定するような発言にならないよう気を付けながら、少しでもその人の気持ちが明るい方に向かっていけるように願いながら発言することを心がける。
- 話をしたタイミングでうまくいかなかった時は、その患者さんが玄関を出てお帰りになるその瞬間までチャンスを伺い続けて、チャンスがなかった場合は思い切り笑顔でお見送りするようにする。
今やっていることが本当にアヒンサーと言えるのかどうか分かりませんが、やり続けた先に体得されていくものだと思うので、今は自分がよいと思うことを根気強くやっていきたいと思っています。

登山中に見つけた杉の切り株から、小さな幼木の芽が芽吹いていました。
ヨーガの聖典『ヨーガ・スートラ』では、アヒンサーについてこう書かれています。
非暴力(アヒンサー)に徹した者のそばでは、すべての敵対が止む。
一人一人がアヒンサーに徹することで、少しずつでも差別や偏見をなくすことができる。穏やかな空気が流れて平安な世界に変わることができる。そうなれるよう、まずは自分自身が徹底して実践していきたいと思います。
ハルシャニー