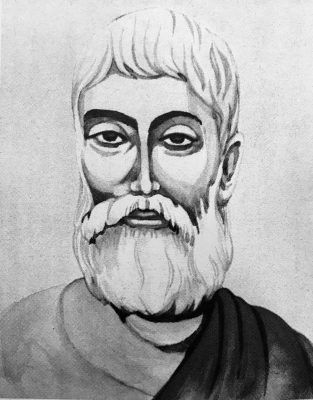シュリー・マハーヨーギーの弟子には、遠方に住んでいて、容易に師に会えない方もいます。京都に住む弟子たちは、直伝クラスに通ったり、サットサンガなどで、よく師にお会いすることができますし、ブログでもご紹介させていただいているように、昨年からは台湾や松山、京都など各地で特別サットサンガも開催していますが、それでもなかなか会えない人はどのようにヨーガへの思いを高め、日々実践していけばいいのでしょう。
それについて、遠く北海道に住んでおられる三井さんが、ご自身の思いと日々の実践について投稿してくださいました。北海道から京都まで容易く来られませんから、三井さんはブログやパラマハンサに掲載される師のお言葉を何回も読まれているそうです。そして、年に一度ヨギさんに会いに来られた時の三井さんの、実に濃密な師との交流シーンが目に焼き付いている方も多いと思いますが、この記事を読むと、物理的な距離や回数ではないということが実証されているように感じます。
まだヨーガに出会っていない頃、よく見る夢がありました。
夢の中で私は、とっても大事なことをしていないことに気づき、これをちゃんと覚えておいて毎日やらなきゃ!と決意するのですが、目覚めた時には、その大事なことが何だったのか全く思い出せないのです。
私は何か、とても大事なことをしていない・・・・・。
そこで、今までよりも注意深く意識しながら生活してみることにしました。大事なことをしていないはずなのに、日々の生活は何の支障もなく過ぎていきました。そしてまた同じ夢を見るという繰り返し。
私は一体何をしていないのだろう?
ヨギさんの下に導かれ、ヨーガを学び、毎日アーサナと瞑想をするようにな ってから、あの夢を見ることはなくなりました。
毎日続けるに値する確かなものを得て、心はようやく安堵しました。私の魂は、ヨーガを渇望していたのだと思います。
ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、歯を磨いたりするのと同じようにアーサナと瞑想も当たり前の習慣になり、何をしていても時間になれば2階の修行部屋へ向かいます。階段を上りながら思うことはただ一つ。
「神は私を待っておられる。もっともっと深い瞑想を捧げよう!」
どんなに離れていても、どんなに会えなくても、心から尊敬できる師と、同じ志を持つ仲間に巡り会えたことは大きな喜びです。
京都に伺い、ヨギさんにお会いした時に伝わってくる神聖なバイブレーションや、慈愛 に溢れた眼差しや、とろけるような笑顔や、ぬくもりのある声は、言葉や文章ではとても伝えられず、実際に味わってみなければ決してわからないことです。
そして、謙虚で穏やかで親切なお弟子さんたちに接すると、頭が下がる思いになります。ヨギさんの教えが深く浸透し、ヨギさんの存在が心にも身体にも染み渡っていると感じます。ヨギさんのお側にいるということは、こういうことかと思わずにはいられません。
ヨギさんのお側でグルバイと一緒にヨーガを学べたらどんなにいいだろうと思う時、頭に浮かぶのはパラマハンサ・ヨガナンダの『あるヨギの自叙伝』の中の一節です。
私はカラ・パトリに、彼の放浪生活について尋ねてみた。
「あなたは冬でも、ほかに着物を着ないのですか」
「着ません。これで充分です」
「あなたは本をお持ちですか」
「いいえ、ひとに物を尋ねられたときは、記憶の中から答えます」
「ほかにはどんなことをなさいますか」
「ガンジス河のほとりを散歩します」
この淡々たる答えを聞いたとき、私の心に、彼の素朴な生活に対するあこがれが強く湧いてきた。私は、アメリカと自分に負わされた重い責任の数々を思い起こした。『いけない!ヨガナンダ』私は一瞬さびしく自分に言いきかせた。『この生涯では、ガンジス河の散歩はお前には許されていないのだ』
この生涯では、ヨギさんのお側でグルバイと一緒にヨーガを学ぶことは私には許されていない・・・・・。
パラマハンサ・ヨガナンダの崇高な使命とは比較にならないとわかっていても、そんなことを考えて寂しくなる時、私を励まし力づけてくれるのは、機関誌『パラマハンサ』に掲載されているサーナンダさんの文章です。
インドの山奥で瞑想行に勤しむヨーギーたちも、社会において多忙な仕事に勤しむ世俗人も、等しく神の思し召しによってその境遇が与えられている。私たちを神の御下に導くための道筋がその境遇にある。
今ある状況は、カルマが要請したものであると同時に、カルマを果たすためにはなくてはならないものであると理解できる。
自分の前にやってくる状況は、すべて神が私たちに与えられる素晴らしい導きなのかもしれない。
肝要なことは、現状に不満を言わず、知足し、淡々とヨーガを実践していくことである。
私たちの真剣なヨーガの実践は必ず神に届き、神はそれを見て慈悲深くもヨーガの道を歩むに必要な熱意と力を与えて下さる。これは真実である。
振り返ってみれば私はずっと、本当のことだけが知りたいと願い、探し求め、これも違う、これも違う・・・と彷徨っていました。もう探し回らなくていいと思うと、深い安心感に包まれます。
お導きくださったヨギさんには、感謝の気持ちでいっぱいです。
サーナンダさんは、「私たちには、戻ることのない長い旅路の覚悟が必要です。」と書いておられます。途中下車することなく最終目的地だけを目指し、風景を楽しみながら長い旅を続けていこうと思っています。
三井








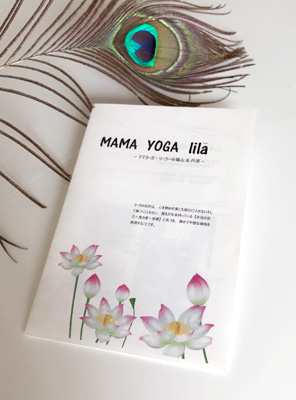 今日、息子が母の洗濯物をたたみながら言いました。「ばあやんが喜ぶようにきれいにたたんであげたい!!」と。そんな息子の純粋な眼差しがとても嬉しく、ヨギさんがそれはカルマ・ヨーガといってとても素晴らしいことだから、お母さんにも、それをいっぱいいっぱいするようにって教えてくださったんだよと話しました。
今日、息子が母の洗濯物をたたみながら言いました。「ばあやんが喜ぶようにきれいにたたんであげたい!!」と。そんな息子の純粋な眼差しがとても嬉しく、ヨギさんがそれはカルマ・ヨーガといってとても素晴らしいことだから、お母さんにも、それをいっぱいいっぱいするようにって教えてくださったんだよと話しました。